忍者走りのランニングフォームが話題になっているのはなぜか
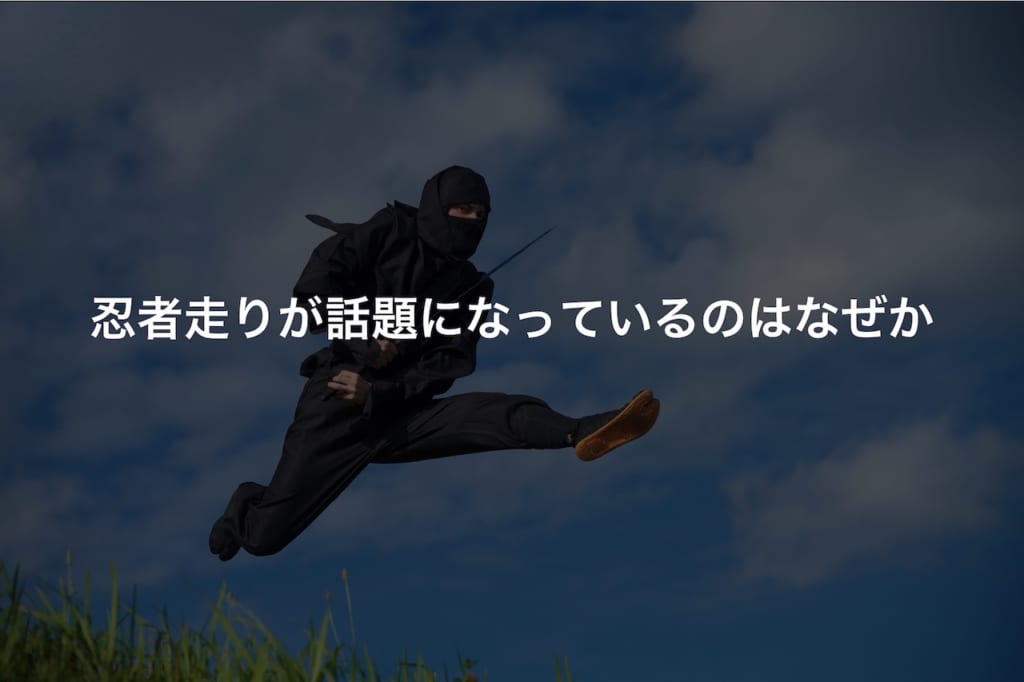
筆者を中心に、「ハーフマラソンまでは何とか自分の走りができる」という方も多いでしょう。
そこで注目されたのが、スズキ浜松アスリートクラブの安藤選手と清田選手の「忍者走り」です。
そもそもこの「高速ピッチ走法」はフルマラソンを走る上で「省エネ走法」として昔から話題にはなっていましたが、今、「忍者走り」が話題になっている理由は「ランナーのスピード高速化」にあります。
ジャンプできる目次
高速化するランナーと故障率の因果関係
筆者はそれほどの走力がないので自信を持っては言えませんが、間違いなく、周囲のランナーは「高速化」が著しいです。
長距離では短いとされる「3kmマラソン」では9分台で走る市民ランナーも珍しくなく、5kmは19分を切っていて当たり前。
10kmマラソンでは34分~36分がもはや“努力すれば叶うレベル”とまでなっている風潮があります。
各々のランナーの高速化が意味することはもちろん、マラソンタイムのインフレ化です。特に競争心が強いランナーにとっては、マラソンタイムが走ることのモチベーションであるという方は少なくないでしょう。
そこで問題になっているのが、「故障率の上昇」です。ビギナーランナーはもちろん、シリアスランナーが必ず“どこかが痛い”ということは、多くのランナーが抱える悩みです。
そして多くのランナーがもれなく“痛みを抱えつつ走っている”という状態でしょう。
高速化するランナーとして多い故障は“走りすぎ”によるものですが、そもそもこの「高速化」自体が、フルマラソンでの走り方に対して「疑問」を抱えるランナーが増えています。
高速化に対する意識が強くてフルマラソンに対応できない
ハーフマラソンまでは、脚の着地衝撃による失速は数少ないものです。
ただ、フルマラソンともなると「30kmの壁」や「35kmの壁」にぶち当たるものです。そこにジレンマがあり、「本来のペースで走ること」=「フルマラソンでの快走率」とはなりません。
たとえば練習までは「35kmまでで大丈夫」という意見が多いです。そしてそこにはほぼ「起伏」のことは書いてありません。
平地の周回コースでキロ4分5秒~10秒で30km走ができても、もしかすれば「起伏」に対応できずにペースを崩すこともあります。要は、「フルマラソンの走り方」と「あらゆるコース」に対応できない走り方になっている危険性があるともいえます。
特にストライドが広く、スピード任せで推進力を得るランナーは、フルマラソンでは多くが「ポジティブスプリット(前半のハーフのペースが速い)」であるケースが多いでしょう。
これは本来の走り方が、ストライドが広く、体の真下で着地していても“着地衝撃が大きすぎる”という走り方になっていることが多いためです。
平地では難なくこなせている設定タイムも、フルマラソン本番になれば気分が高揚し、多少のアップダウンに対して慎重になっていない、あるいはペースが速すぎるという「罠」に陥りがちです。
結論から言えば、フルマラソンでの走り方と日ごろのスピードレースの走り方では、少し意識の違いを変えなければいけないということです。
スピードランナーも「忍者走り」への意識を
32という筆者での年齢はともかく、多くの20代ランナーはスピードが速いレース展開を好みがちですよね。
「どうやればゆっくり走ることができるの?」という悩みを持った若いランナーは多いんですが、これは茶化しているわけでもなく“本当にゆっくり走ることができない”んです。
そもそも駅伝からハーフマラソンまでのタイム短縮には「ダイナミックな動きづくり」が練習内容にも含まれることが多いです。
結局、そのダイナミックな動きが身にしみているかぎり、「地面の反発からのエネルギー」と同時に、「地面の反発からのダメージ」も高くなっています。
これを解消するために参考にしたいのが「忍者走り」です。
上下動が少なく、足の回転が速いピッチ走法は、地面からの着地衝撃をうまくロスできています。
省エネ走法の特徴
- 肩甲骨はうまく動かせている
- 肩に力が入っていない
- 肘をコンパクトにたたんでいる
- 肩甲骨と体幹、骨盤の連動がスムーズ
- 脚は振り上げずに、前進運動を「全身」で可能にする
- 着地のロスが大幅に少ない
スピードランナーの特徴
- 肩甲骨と腕振りにより推進力を得る
- 体の捻りが大きい
- 上半身も骨盤も前傾している傾向がある
- 脚の振り上げが大きく、四頭筋からハムの筋力をフル稼働させる
- 着地は真下でも、着地音が大きい
- 大跳び
もちろん、マラソンのタイムを向上させるためには“2つの融合”が適切なランニングフォームでしょう。
ただ、筋力や骨格、フォームの癖は十人十色なので、必ずしも「これが正解」という式と答えがないのが、多くのランナーを悩ませている「フルマラソンでの失速」につながるのではないでしょうか。
もちろん練習量も必要ですが、まずは動きという観点から見直すのも大事だと言えそうです。
スピードランナーが多く苦労する「フルマラソンの走り方」は、通称・「忍者走り」での省エネ走法を意識することも、フルマラソンタイム向上のヒントと言えるでしょう。
清田真央選手の忍者走り
名古屋ウィメンズマラソン2017にも出場し、独特のフォームを見せる清田真央選手。
ヒールストライカーで、腕もほとんどふらない「忍者走り」なんですが、フルマラソンでは理に適っている理由があるんです。
上下動が少ない!無駄のないランニングフォーム
156cmで、どちらかといえば小柄な清田真央選手。
名古屋ウィメンズでも先頭集団をひた走る清田真央選手の走り方に「独特!」と思った方も多いのではないでしょうか。
本人曰く「忍者走り」とも言われるフォーム、実は長丁場のフルマラソンでは理に適っているんです。
そもそも42.195kmの距離では、いかに上下動運動を失くすか、ということも大事です。
男子ケニア人ランナーでも、ストライドは大きいように見えて、全く“ブレがない”のもケニア人ランナーが強い秘訣。
ランニングは前進運動で、いかに地面から反発を得て無駄なく前に進むことができるかも「省エネ走法」ではかかせないことです。
清田真央選手はその点、上下動がまったくなく、地面の反発をうまく使ってスピードを出すフォームのいい例ともいえますよね。
ヒールかフォアかは着地では重要ではない!?
「かかと着地」 or 「つま先着地」は、多くのランナーが気にしていることでしょう。
特に数年前からケニア人に多い「フォアフット」にしようとするランナーが多いですが、清田真央選手はどちらかといえば「ヒールストライク」です。いわゆる、「かかと着地」に近い形。
実は大事なのは「着地点」ではなくて、着地したときの骨盤の位置なのは多くのトップランナーを見れば一目瞭然です。
骨盤が前傾していて着地点が体の真下である場合、地面からの衝撃を少なくして反発を得ようとする動きで、自然とフォアフットになるというのが正しいというのが、筆者の持論でもあります。
腕は振らなくてもバランスが取れればいい?
ランニング運動で腕振りが重要なのは、以下の点からです。
- 肩甲骨が動くから
- 上半身を起点として脚の振り上げが必要なため
- 肩甲骨(上半身)と骨盤(下半身)の連動
- 体幹から四頭筋への動きを生むため
- 着地のバランスを取る
つまり、肩甲骨→体幹→骨盤→四頭筋やハム→着地の運動に大きなダメージがなければ、ダイナミックに腕を振る必要はないともいえます。
ただし、体重が軽くなければ難しいというのも難点。特に筆者のように、練習嫌いで、食う・寝る・食うの4拍子が揃っているランナーは、腕振りのメカニズムと同時に、しっかりとした練習も大事でしょう。
安藤友香も腕を振っていない!
清田真央選手と同じ、スズキ浜松アスリートクラブの安藤友香選手も同じようなコンパクトな腕振り。
ダランとウデを下げるフォームに、「このフォームで速く走ることができるの?」と疑問に思っている方も多いはずです。
ただ、問題はいかに地面からの反発を無駄なく得るかなので、走るという行為を一度、フラットな視点で考えてみてはいかがでしょうか。
そんな安藤友香選手、まさか(!?)の日本人1位で、そのタイムは「女子初マラソン歴代1位」で「マラソン女子記録歴代4位」の素晴らしい記録!
2時間21分36秒は、さすがに「すごすぎる」としかいいようがありませんよね。
世界陸上にも内定し、日本人2位(総合3位)の清田真央選手も世界陸上にほぼ行けるタイム!(2時間23分47秒)
世界陸上はもちろん、2020年の東京オリンピックも楽しみですよね。
忍者走りのまとめ
名古屋ウィメンズマラソンでも好走を見せた清田真央選手・安藤友香選手。
スズキ浜松アスリートクラブの二人の今後の活躍が楽しみですよね。
二人で世界陸上を走る姿、ぜひぜひ見たいところです。
なお、ダイナミックなフォームで着地衝撃がありつつも、フルマラソンを走りきる筋力を身につけるのに有効とされるのが「起伏走」や「下り走」だと筆者は自分に課題を立てていました。
筆者は今は満足に走ることができない体の状態ですが、来期のフルマラソンをすでに見据えているランナーは「オーバーホール」をしつつも、下り走や起伏走を練習で意識してみてはいかがでしょう。
特に、着地衝撃に耐えうる「四頭筋」と「ハムストリングス」では、下りで思い切って走る練習が効果的です。
ただ、下り走ではきちんと「前傾」して、「体の真下で着地する」ということができず、のけぞった姿勢で下ると故障率も高いです。
「忍者走り」の秘訣は、上半身をいかに脱力させて、高速ピッチでいかに推進力を得るために地面からの反発を得ながら、ダメージを殺すということです。
うまく「忍者走り」の良い点も吸収したランニングフォームを作り上げたいですね。
この記事を書いた人

- → 広告掲載について





